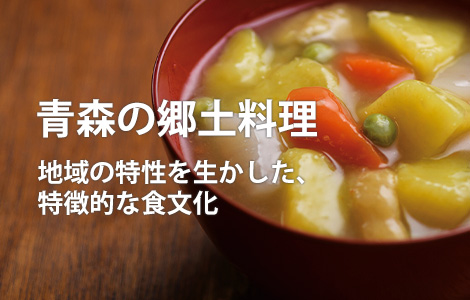青森の冬は雪深く2月になると毎日のように雪が降ります。雪かきは大変ですが、この雪がきれいな水になり、豊かな大地を作ります。
今回は、雪や冬の寒さを利用して生産されている「青森の冬野菜」を紹介します。
青森の冬野菜
冬は寒さが厳しくて一面銀世界の青森県ですが、いまの季節でもビニールハウスや雪をかぶった畑の中で、多くの野菜が作られています。
冬の野菜はゆっくりと育つので収穫するまで日数はかかります。しかし冬の寒さに耐えて育つため、野菜自身が糖分やアミノ酸などの濃度を高めており、その分、甘みがあって栄養価の高い野菜に仕上がります。
また、冬は病害虫の発生が少なくほとんど農薬を使わずにすむため、安全・安心な野菜をお届けできます。



北国ならではの魅力がたくさん詰まっている「青森の冬野菜」の一例を紹介します。
ふかうら雪人参(露地栽培)
通常、人参は、種を播いてから約100日程度の栽培期間を経て秋頃に収穫します。「ふかうら雪人参」は秋に収穫適期を迎えた人参を、さらにそのまま土の中で越冬させて、雪の下でじっくり熟成させてから収穫しています。
もともと寒さや乾燥に強い人参ですが、雪が降り寒くなると、凍らないように自らの体内に糖分を蓄えることによって糖度が上がるため、果物にも引けをとらないフルーティーな甘さが生まれます。「ふかうら雪人参」は、熟成された甘みに加え、人参特有の青臭さがほとんどないため、料理はもちろん、生絞りジュースにしてもおいしく食べることができます。


【オススメ調理方法】
人参に含まれるカロテンは芯よりも外側に多いので、よく洗って皮付きで調理するか、できるだけ薄く皮をむいて使うのがオススメ。カロテンの吸収率は油で調理することで高まります。
寒締めほうれんそう・小松菜(無加温栽培)
「寒締め」とは、収穫間近になった菜っぱ類(ほうれんそう、小松菜など)をわざと寒さにさらす寒い地域限定の栽培方法です。秋の終わりころからハウスを徐々に開放しながら一定期間寒さにあてます。そうすると糖分などの凍りにくい成分が蓄積し、低温への備えができあがると言われています。葉は凍りつかないように水分を少なくし、糖分をため込むことから甘みが増し、うまみ成分が高まりおいしい状態になります。
寒さに弱い野菜はこの働きが弱く凍って細胞が壊れ枯れてしまいますが、寒さに強いほうれんそうなどは寒締め栽培に適しています。


【オススメ調理方法】
寒締めしたほうれんそうなどは、そのままおひたしで食べると素材そのものの甘みと旨みを楽しめます。また、バターやチーズ、ホワイトソースなどのこってりとした味付けのグラタン、パスタなどとも相性抜群です。
冬陽(ふゆび)春菊(加温栽培)

積雪が多く日照が少ない冬の津軽地方。この気象を逆手にとって弘前市の小堀農園では温泉熱を利用したハウス栽培に取り組んでいます。冬のやさしい日差しが、柔らかくてアクの少ないまろやかな春菊を育みます。さらに、夏の間の徹底した土づくりや、減農薬・減化学肥料栽培へもこだわっており、冬陽春菊のブランドで県内はもとより首都圏でも親しまれています。
【オススメ調理方法】
鍋物料理を食べることの多い冬に需要の多い春菊ですが、主にすき焼きや湯豆腐、たらちりなどに利用されます。熱を加えすぎると、独特の風味と香り、栄養素が損なわれるため、さっと熱を通して食べるしゃぶしゃぶもオススメです。
促成アスパラガス(伏せ込み促成栽培)
春から秋まで畑で太陽をあびながら栄養たっぷりに育ったアスパラガスの株を冬直前に掘り出し、ハウスの中で加温しながら栽培したのが「促成アスパラガス」です。ハウスの中にトンネルをさらに設置し、土中に埋めたパイプにお湯を流したり、電気による温床線で根っこの部分を加温するので、ハウス全体を暖めるのに比べると燃料代を抑えることができます。夏場に蓄えた養分だけで育てるほか、農薬を使用しないので、安全・安心です。甘みが多く、えぐみや苦みが少ないのが特徴です。


【オススメ調理方法】
根本のごく硬い部分だけを切り落とし、硬い皮はピューラーなどを使って削り取ると捨てる部分が少なく、おいしく食べることができます。新鮮なものはあまり熱や手を加えず、シンプルな料理で素材そのものの味を楽しむのがオススメです。
北国ならではの栽培方法で生産されている「青森の冬野菜」。この季節にしか出会えない、甘みと旨みを増した野菜の味を是非お試しください。